今回は小説『逃亡者は北へ向かう』柚木 裕子(著)のご紹介!
東日本大震災を舞台に、ちょうどその時期に凶悪事件を起こしてしまった登場人物の逃亡劇を描いた作品。
震災と凶悪事件がほぼ同時に起きた。被災者たちは限られた情報の中、避難所生活をしていた。事件を起こした犯人もその土地を訪れると震災の傷跡に直面していく。逃亡者はなぜ北へ向かうのか?
書籍の情報を以下にまとめます▼
INFO
タイトル:『逃亡者は北へ向かう』
著者:柚木 裕子
出版社:株式会社 新潮社
発売日:2025年2月
メモ:東北地方を描いた長編作品
あらすじ
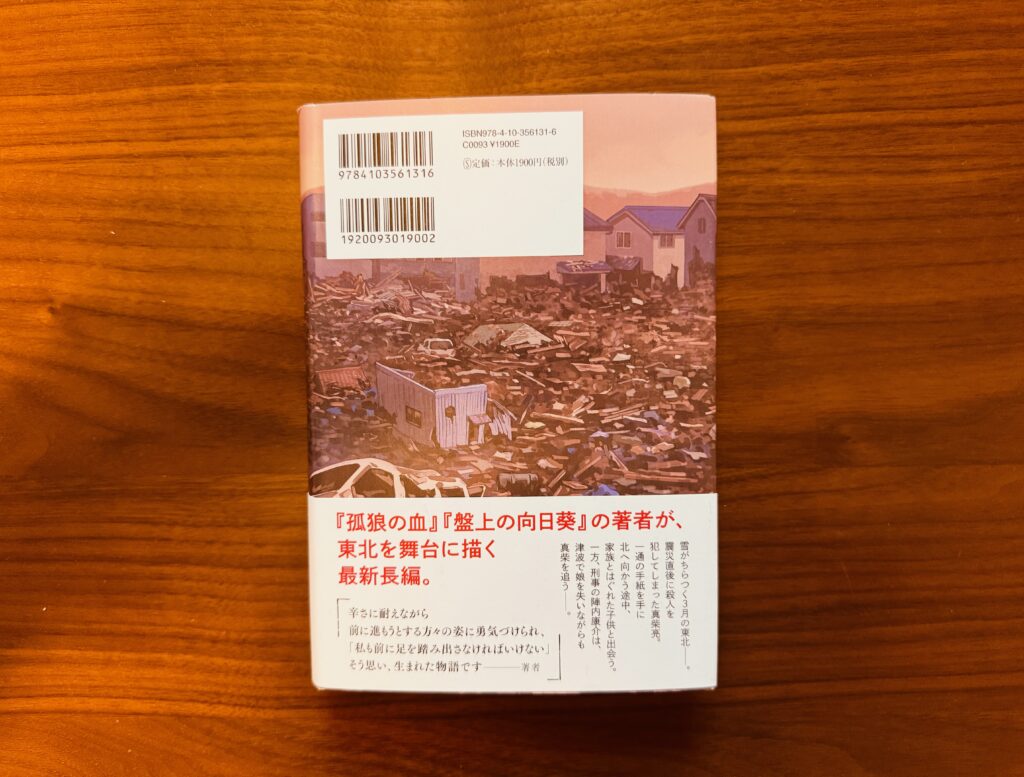
雪がちらつく3月の東北ーーーーーー。震災直後に殺人を犯してしまった真柴亮。一通の手紙を手に北へ向かう途中、家族とはぐれた子供と出会う。一方、刑事の陣内康介は、津波で娘を失いながらも真柴を追うーーーーー。
『逃亡者は北へ向かう』裏表紙より
読書感想

孤独は言葉をなくしていく
休日、私は家から自転車で20分くらいのところにある漫画喫茶に行った。そこの漫画喫茶は、ネットで予約をしておけば入店後、直接個人スペースへ向かうことができる。誰とも接することなく利用ができるのだ。店内を見て回り、気になった漫画作品の第一巻を数作品手に取る。ドリンクバー付きのプランを予約していたため、まずはホットコーヒーをチョイスした。以前この店を利用した際、漫画本を読み始めるとウトウトしてしまった。気が付くと爆睡。起きたころには利用時間の大半を寝て過ごしてしまっていた。それ以来、一杯目はホットコーヒーと決めている。
席について漫画本を読み始めたのだが、なかなか続かない。初めて読む作品は、軌道に乗るまで持たない傾向がある。よくドラマとかでも、第一話だけ見て面白いかどうかを判断すると聞いたことがある。日本人のだれもが知る有名作品は、面白さのレッテルの効果もあってか、自然と巻数を重ねることができる。気づくともうこんな時間なのかと、物語の世界から現実へと引きはがされる感覚を何度も経験した。漫画をよく読む身からすると、誰しもが知る作品はもう読み飽きている。自分だけの新規開拓作品を見つけ出すことが最近のブームなのだ。
しかし、物珍しそうな作品は、作中のストーリーも独特なものが多く、なかなか自分の好みに合ったものに出会うことができない。少し読んではやめ、少し読んではやめを繰り返していくうちに、テーブルの上は途中でやめてしまった漫画本が積みあがっていた。新しい作品を探しに行くのもめんどくさくなった私は、備え付けのパスコンからネットにつないだ。
普段利用している不特定多数の人たちを会話ができるチャットルームアプリを起動する。そのチャットルームアプリには様々なジャンルごとにチャットルームが開設されていて、日々、不特定多数のユーザがざっくばらんなやり取りをすることができる。私もよく利用するのだが、すでに「漫画」に関するチャットルームで複数人のユーザがやり取りをしているようだ。
「現在、漫画喫茶にきている。〇〇って作品と〇〇を読んだけど、5ページで無能作品に認定」私は途中でやめた作品を横目にチャットルームに投稿を行った。「ちなみに、〇〇においては、4ページで限界」立て続けに投稿した。トイレに行って用を足してきた後、そのチャットルームを見ると、私の投稿を境に数人のユーザが退室していることが分かった。
「漫画って退屈しのぎにしかならない。あと最近は、読めば読むほど、時間の無駄遣いだなって思うし、漫画一冊のコスパって悪くねぇ?って思う」すると別のユーザから「暇なんですね」との投稿。それに対して私は「このチャットルームに来ている時点で同類。自分だけは違うって思うな」間髪入れずに投稿した。するとさらに別のユーザから「このチャットルームは漫画好きの交流の場であり、漫画を蔑む場ではありません」はいはい、優等生タイプの登場ね。「運営側でもないのに偉そうなことを言われても。自分の望み通りになると思っているなら大間違い。思想は人それぞれ異なったものを有している。それを具体化するのは個人の自由」この投稿をしてしばらくすると、画面上に「あなたはチャットルームから強制的に退出させられました」とのメッセージが表示された。
乱暴にパソコンの画面を閉じ、横になる。天井を見ながらボーっとしていると、熱くなっていた感情は次第に落ち着きを取り戻していった。顔も名前も知らない誰かとのやり取り。その中で言い争いに発展した。口は全く動かさず、パソコンのキーボードを叩いて言葉を紡ぐ。奇怪な様子は自分でもよくわかっていた。「そういえば、今日起きてから誰とも話していないな」独り言さえ呟いていない自分は、言葉を発することを忘れてしまうのではと心配になる。漫画喫茶を後にするとき、店員に「ありがとうございました」と言ってみた。かすれた声は、不完全な音として相手まで届かず、床に落ちていった。
遠い地でも
高校3年生の私は学校も自由登校になっていることもあり、実家のリビングで午後のワイドショーを見ていた。連日学校が休みということもあり、午後のこの時間帯は、暇を持て余すそんな時間だった。ワイドショーが取り上げていた内容もろくに聞いておらず、ぼーっとしていると、体にかすかな揺れを感じた。「あっ、地震かな?」と思う間もなくその揺れは大きなものへ変わった。その揺れは、18年間生きてきた中で最も大きな揺れであることは間違いなかった。
1階のリビングにいた私はとっさに外へと続く窓を開けた。外の様子をうかがうと、庭に停めてあった軽自動車が車内で人が暴れているかのごとく揺れていた。目線の先の電線も波打っている状態だ。当時家にいた母親、祖母とともに庭に避難した。幸いけが人はなく、家の状態も問題はなかった。私たちが暮らしていたのは神奈川県の〇〇市。テレビの速報では震度4強を記録していた。
しばらくすると、当時中学生だった弟が興奮しながら帰宅してきた。学校からの帰宅途中で地震があったようで、「地面に這いつくばって耐えた」とのことだった。ここまで大きな地震にあったことがない私は、弟の安否確認の必要性を弟が帰宅してから気が付く始末であった。地元の企業に勤めていた父親はそんな日に限って都内へ出張。日帰りの予定だったが、結局帰宅困難者となり、次の日になって帰ってきた。
地元で経験した震度4強の地震はテレビの報道によって、東北地方を震源とする巨大地震であったことがわかった。地震は沿岸地域に壊滅的な被害をもたらした。津波による被害は私たちの想像をはるかに超えるものであり、絶望感と喪失感は遠く離れた地にも色濃く漂っていた。沖合で発生した津波が横一列となって陸に迫ってくる。上空からとらえた映像は現実感がなく、作り物のシーンにさえ見えた。
この大震災は様々な影響をもたらした。ポジティブにとらえようにもそれらの影響は私たちにとってプラスになるものは何一つ存在しなかった。当時を連想させるものから人々は離れていった。復興という言葉が掲げられた地区のゴールはいったいどこなのだろうか?土地を復興させ、いつも通りの日常が送ることができれば人の心も自然と癒されていくのだろうか?
遠い地で経験した私たちの思いはあまり語られることはない。語ることに抵抗を感じる人もいるだろう。しかし、同じ国に住み、あの年のあの日、あの時間に地震にあったことは事実である。あの出来事によって私たちのあるべき日常も少なからず影響を受けた。災害に対して無力な私たちは、自然の成り行きに従わなければならい。その時のために心の準備をしておくのか?いや、そんなことはしたくない。明るい未来に心を馳せる。
それぞれの顔
テレワークが一般的になってきたこの時代に、私は自分のポリシーとして会社に出社することを日課としている。家から会社までは電車を使って1時間弱。決して近いとも言えないが、そんな遠くもない。これくらいのバランスがちょうど良いのかもしれない。
私の仕事は就業時間に多少遅れてもうるさく言われることもないため、大体10分くらい前に着くように家を出発している。時々、電車遅延に出くわすと確実に遅れてしまうのだが、そんなことはお構いなし。寝坊もせず、家を出ているのだから何が遅刻だ。むしろいつもよりも堂々と出社している。
今日もいつも通りの時間に仕事を終え帰り支度をする。定時に帰ることに引け目を感じていたのはいつまでだっただろうか。仕事に縛られない考え方を身に付けてから、定時に帰宅することになんとも思わなくなった。結婚をして子供もいる私にとっては、家に帰ってからも仕事以上に頑張ることはたくさんある。それが人生であり、仕事も家のことも人生という大きな枠に収まる一つでしかないのだ。
電車に乗り、自宅へと向かうにつれ、私はサラリーマンの顔から父親の顔へと変わっていく。人それぞれあると思うが私の場合、部屋の明かりのスイッチのようにONとOFFを瞬時に切り替えることができない。例えるなら、エアコンのようにスイッチを入れてから徐々に部屋の空気が変わっていくような、そんな感じでサラリーマンとしての自分から父親としての自分に変わっていくのだ。
だからこそ、私はテレワークではなく、今でも片道1時間弱かけて仕事場へと向かっている。この時間があるからこそ、頭の中が整理され気持ちの切り替えがうまくいっている。それでもコロナ禍ではテレワークを余儀なくされた。時間に多少の余裕は生まれたものの、仕事とプライベートでうまく感情をコントロールすることができなかった。家族で夕飯を食べている最中に仕事のことが気になり、パソコンを覗き込んでしまうこともしばしば。4歳になる娘も妻に対して「パパ、忙しそう」と呟いたりもした。
最寄りの駅から家までは歩いて10分くらい。あたりは駅前の喧騒から離れ、住宅街へと変わっていく。目線の先に自宅が見えてきた。今日も自分の帰りを待っているかのように玄関には優しいオレンジ色の光が灯っている。それを眺めたとき、私は完全に父親としての自分に切り替わる。
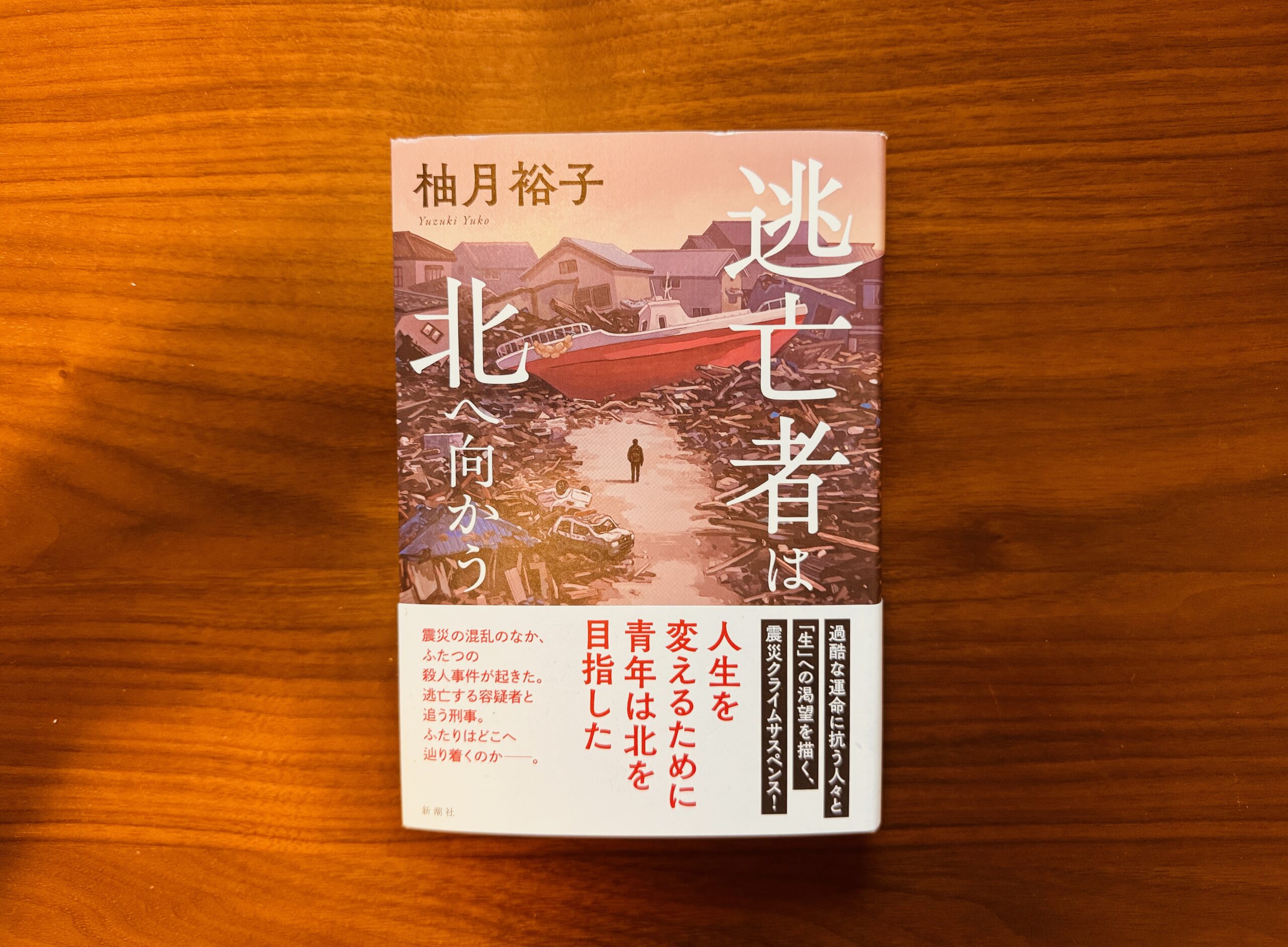
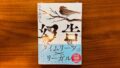

コメント